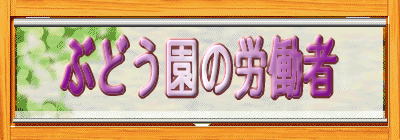
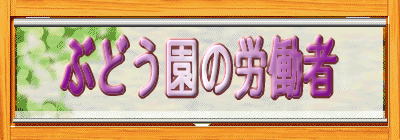
| マタイによる福音書 第20章1〜16節 | |
| 「天の国は次のようにたとえられる。 ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。主人は、1日につき1デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。 また、9時頃行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、 『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』 と言った。それで、その人たちは出かけていった。 主人は12時頃と3時頃にまた出て行き、他の人々が立っていたので、 『なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか』 と尋ねると、 彼らは、『だれも雇ってくれないのです』 と言った。主人は彼らに、 『あなたたちもぶどう園に行きなさい』 と言った。 夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、 『労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』 と言った。そこで、5時頃雇われた人達が来て、1デナリオンずつ受け取った。 最初に雇われた人達が来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも1デナリオンずつであった。それで、受け取ると、主人に不平を言った。 『最後に来たこの連中は、1時間しか働きませんでした。丸一日、暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは。』 主人はその一人に答えた。 『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしては、いけないのか。それとも、わたしの気前の良さをねたむのか。』 このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」 |
YACCOのつぶやき
人生の日時計
”働く”ということには、二つの側面があると思います。一つは「自分の生活のため」、そしてもう一つは「社会に貢献するため」です。言い方を換えれば「自分のため」と「人のため」ということになります。経済的な意味でも、精神的な意味でも何かのためになること、それが労働です。なんのためにもならない徒労に精を出す人はいないでしょう。 そして誰かのために行う”労働”は、「やり甲斐」と「生き甲斐」を生み出します。それは他者を生かすことであったり、喜ばせることであったり、誰でもができない困難な事業を達成することだったりするかもしれません。もちろん、誰もが自分の望んだ仕事に就けるわけではありません。むしろ、そういう人の方が少ないのかもしれませんが、誰もが自分が今得ている仕事の中に、自身のやり甲斐を見いだそうと務めていることに変わりはないでしょう。 例えば魚屋さん。魚屋さんは、私たち消費者が早朝に鮮魚市場に買い付けに行けない代わりを担ってくれています。魚市場は魚屋さんが一艘一艘の漁船に鮮魚を買い付けに回れない代わりを担っています。漁師は市場の職員がいろいろな種類の魚介類を海に捕りに行けない代わりを担っています。こんな風に、さまざまな仕事がつながりながら、最終的には消費者の食卓で人の命を支えていることを、間で働く誰もがやり甲斐として意識しているのではないでしょうか。そして、私たちはそうした働きの報酬として生活費を得ているのです。 報酬は多ければ多いに越したことはないのかもしれません。多ければそれだけゆとりがあるように感じられるからです。しかし、私たちは何を基準に”ゆとり”を量っているのでしょう。 ”人並み”という言葉があります。そして、”人並み以上”という言葉があります。プール付きの豪邸に住みたいとまでは思わなくても、「せめて人並み以上には・・・」と考えている人が多いのではないかという気がします。でもそれって見方を変えれば、人並みという基準に対して優位に立とうとする差別化を求めていると言えなくはないでしょうか。  「ぶどう園の労働者」のたとえを、そのままに読んでしまうと実に非常識です。確かに、元々の契約が時給契約でなかったとはいえ、早朝から働いている者と、終業寸前に数分の働きしかしていない者が同じ報酬というのは、常識では納得がいきません。それを、オーナーに「自分の金を自分の好きに使って何が悪い」と開き直られたら、翌日ぶどう園で早朝から働こうと思う者はいなくなり、多くの者が終業時刻ぎりぎりに殺到することになってしまいます。しかし、このたとえに”明日はない”のです。 「ぶどう園の労働者」のたとえを、そのままに読んでしまうと実に非常識です。確かに、元々の契約が時給契約でなかったとはいえ、早朝から働いている者と、終業寸前に数分の働きしかしていない者が同じ報酬というのは、常識では納得がいきません。それを、オーナーに「自分の金を自分の好きに使って何が悪い」と開き直られたら、翌日ぶどう園で早朝から働こうと思う者はいなくなり、多くの者が終業時刻ぎりぎりに殺到することになってしまいます。しかし、このたとえに”明日はない”のです。このたとえで語られている「明け方から夕暮れまでの時間」は、「人の一生」を日の出から日没までに比喩したものです。人生の明け方、つまり乳幼児期に洗礼を受けクリスチャンとなった者もあれば、午前9時の思春期、青年期にクリスチャンになる者、正午や午後3時の中高年でクリスチャンの輪に加わった者もあります。そして、日没直前のいまわの際で洗礼を受け神の子とされる人だってあるでしょう。もちろん、人それぞれ人生の日時計の長さは一定ではありませんから、人によって日没までの長さも異なります。人によっていつが午前9時で、いつが夕暮れなのか、それは神のみぞ知ることです。 そして、「労働」は洗礼を受けて「クリスチャンとなってからの奉仕」を比喩しています。そう考えると、「ぶどう園」は「教会」と考えることができるように思います。そして、「農園の主人」は「主イエス様と三位一体なる神様」を意味しています。 では、夕暮れ、つまり人生の終わりに与えられる「1デナリオンの報酬」とはなんなのでしょう。それは、聖書に約束された「永遠の命」のことであり、これ以上ない最高の報酬を意味します。それでもなお、朝早くから働いた労働者は「私の方が、主(人)のために長く奉仕したのだから」と、より多くの報酬を要求します。しかし、「永遠の命」に優る報酬は他にないのです。イエス様がたとえの中で、この登場人物に、あえてそのように言わしめたのには、ある意図があったと考えられます。それは、「主のための奉仕のはき違え」に対して示唆を与えることでした。 ここで、もう一度思い起こしてください。労働によって生み出されるものの中に「やり甲斐」と「生き甲斐」があったということを。 クリスチャンとして主のために奉仕すること、それは苦役ではありません。なぜなら、それぞれが与えられた賜物(たまもの)を用いて、主に喜んでいただくための奉仕に身を捧げる時には、仕える私たちにも喜びが満ちあふれるからです。 もちろん、奉仕の業に困難がないわけではありません。自分の力ばかりに頼りすぎると、なかなか達成できなかったりします。だから、主に助けていただかなければならないのですが、主の助けをいただいて達成できた時には、自分一人の力だけで達成した時の数倍、数十倍の恵みと喜びをいただくことができます。 つまり、主に仕えること自体に恵みがあり、クリスチャンとして神に奉仕する私たちには、既にその恵みが与えられているということを思い起こす必要があるのです。言い方を換えれば、それを「地上の恵み」と呼ぶことができるかもしれません。 ですから、教会におけるクリスチャンの営みは、「おつとめ」でも「苦行」でもありませんし、永遠の命という報酬を得るために、多くのことを我慢して、無理を押して日曜日に教会に集っているわけでもないのです。むしろ恵みをいただくために、皆がこぞって喜びいさんで教会へと足を運んでいるのです。そのようにして、頂いた「地上の恵み」に満たされながら、喜びと感謝に溢れた人生を歩み、永遠の命へと至らせていただく者、それがクリスチャンなのです。 その「地上の恵み」に人生の早朝からどっぷりと浸からせていただく者もあれば、青年期、壮年期そして晩年になってから呼び寄せられる者と、主イエス様との出会いの時期は人によってまちまちです。 「救い」は一人ひとりの”訓練”や”行”や”経験の長さや量”に応じて与えられるものではありませんし、主はそうしたことで報酬を差別される方ではありません。御子を信じる者に等しく「最高の報酬=永遠の命」を与えてくださいます。 あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ(口語訳聖書:伝道の書12章1節)とは、人生の日時計の少しでも早い時刻から、地上での祝福された人生のうちに身を置きなさいとの、神様からの勧めなのです。 |